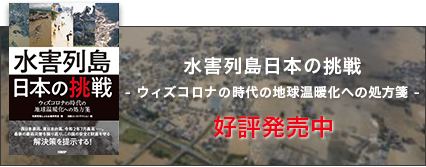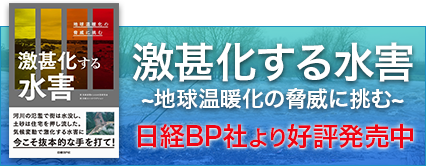参議院災害対策特別委員会 理事懇談会
1月10日(水)、参議院災害対策特別委員会 の理事懇談会を開催し、内閣府防災をはじめ関係省庁から能登地震の被災状況などについてご報告をいただき、それを踏まえ各会派の理事が質疑を行いました。
自民党を代表して私から、今後の地震の見通しについて伺い、震度6弱や6強の可能性も否定できないことをしっかり伝えるようお願いしました。
また、被災状況の全貌把握に向けて、取り組みを加速するようお願いしました。また、立ち入りが困難な地域については、航空写真を活用した被災状況の把握にも取り組むようお願いしました。
また、能登半島では道路事情が悪くアクセスに問題があること、大きな余震が続いていること、大雪に見舞われる可能性が高いこと、被災した家屋の修復が難しいことなどから、一時的に金沢市や富山市などより安全な地域に避難する「広域避難」の検討を進めるようお願いしました。内閣府防災からは前向きに進める旨お答えをいただきました。
今後とも、被災地の安全確保と早期復旧に頑張ってまいる所存ですので、皆様のご支援をよろしくお願いいたします。